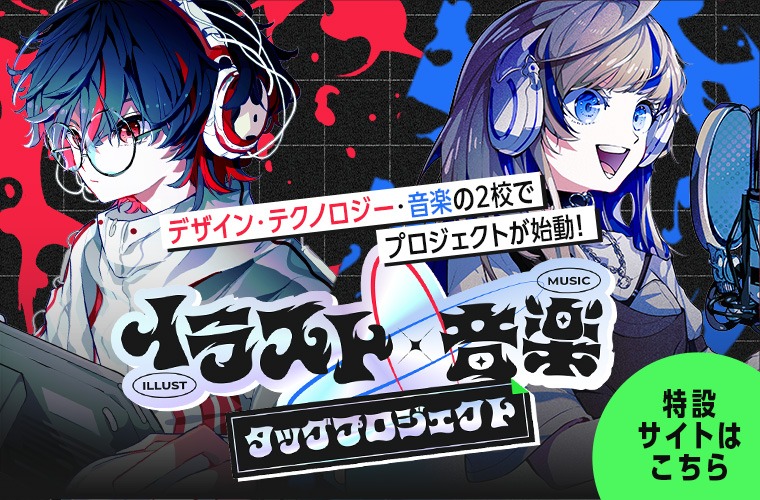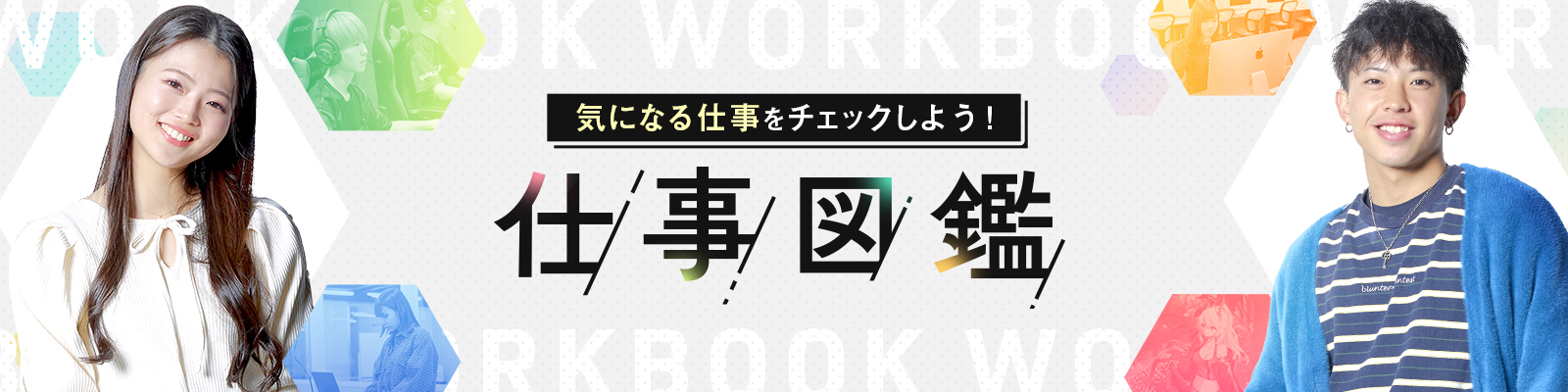漫画家とは
雑誌やWebサイトで作品を連載し読者に届ける
みなさんもご存知の通り、漫画家は雑誌やWEBサイトで漫画を連載し読者に届ける職業です。
世界でも有数の漫画文化をもつ日本では多くの漫画が存在し、ファンタジー、恋愛、スポーツ、ギャグなど作品のジャンルも幅広いです。
ストーリー制作と作画両方を行うため難易度が高く、ストーリーを考える「原作」と絵を描く「作画」で役割分担する場合もあります。
作品の人気が高まるとメディアミックス展開でアニメ化やドラマ化することもあり、時には社会現象を起こすことも。
アニメ・ゲームと並び海外での人気も高く、文化を超えて盛り上がるコミュニケーションツールのような役割を果たしている作品もあります。
漫画家の仕事内容
自分の考えたストーリーを漫画で表現する

漫画家の仕事は自分の頭の中にあるストーリーから漫画の原型であるネームを作り、そのネームをもとに作画することです。
自分のアイディアを読者にわかりやすく伝えるために、構成、作画表現、コマ割り、セリフ回しといった技術を駆使して作品を完成させます。
週刊や隔週、月刊など連載のペースはさまざまですが、ページ数や締切といった制約と作品のクオリティを両立させることが求められる仕事です。
作画は手間と時間がかかるのでサポートのためアシスタントを雇うことも多いです。
アシスタントに背景や小物、モブキャラの作画やトーン貼りを任せ、自身はネーム制作やメインキャラの作画に集中するといった分業体制がとられます。
漫画家の収入は主に原稿料と単行本の印税となりますが、ヒットするまでは収入が安定しないので上手くやりくりすることが大切です。
また、担当編集者との協力も重要です。アイディアだしやネームチェックをしてもらうことで読者目線を取り入れ、読者にとっておもしろい作品へと完成度を高めます。
ネーム
- 漫画では最初にネームを作ります。
ネームではコマ割りやキャラの配置、セリフといったレイアウトを大まかに決めます。
原作者がいる場合このネームの状態で原作を渡されることも多いです。
下書き
- ネームを参考にキャラクターや背景を描き込んでいきます。
構図の調整などもここで行います。
ペン入れ・トーン貼り
- 下書きをペンでなぞり、線の太さや濃淡を調整して立体感や迫力を出します。
また、トーンと呼ばれる柄のついたフィルムを使い陰影をつけたり感情を表現します。
仕上げ
- 黒く塗りつぶすベタ塗り、集中線などの効果線、セリフの文字入れ作業を行い作品を完成させます。
作品全体を見直し必要があれば修正します。
入稿
- 完成した原稿を編集者に届けます。
今はデジタル原稿が主流なので入稿ではデータを送信・共有することが多いですが、アナログ原稿の場合は郵送で編集者に送ります。
漫画家になるには
漫画家への道のり

漫画家になる方法は漫画家として連載デビューすることです。
編集会議で連載にOKをもらう必要があるので高いハードルですが、ここが目標となります。
多くの漫画家は出版社への持ち込みや新人賞を経てデビューしているので編集者の目に止まるような実力を磨きましょう。
漫画スキルを身につけるには美大・専門学校・独学といった方法があります。
それぞれ長所・短所があるので
・本格的な美術を学び作画の技巧・表現力を磨きたければ美大
・イラスト、作劇、デビューなど漫画スキルに特化した勉強をしたいなら専門学校
・先生を必要とせず、自分のペースで学び費用も抑えたいなら独学
といった進路を選ぶとよいでしょう。
連載デビュー前に別の漫画家のもとでアシスタントをすることも多いです。
アシスタントを経験することでプロの仕事やアシスタントの使い方を学べるので自分が連載を持った時の役に立ちます。
いざ連載がスタートしたら締切という時間制限の中ネーム作りや作画をすることになります。しっかりと準備をして連載を迎えましょう。
求められる知識・資質
作画力
- 漫画の作画には画力以外にもコマ割りや視線誘導、構図といったテクニックが必要となります。
マネジメント力
- アシスタントを雇う場合、仕事の割り振りやスケジュール管理、予算の管理などを漫画家自身がしなければなりません。
スムーズな職場運営のためのマネジメント力を磨きましょう。
スケジュール管理
- スケジュールを管理し、締切を守ることが大切です。
編集者とも協力し無理のない作業環境を整えましょう。
集中力
- 連載作家は締切のプレッシャーのなか作業をこなさないといけません。
集中して仕事にのぞみ締切とクオリティを両立させましょう。
必要な資格・試験情報
資格を取得して一般的な漫画制作について知っておくと複数人での作業で便利
漫画家になるのに必要な資格はありません。実力主義の業界なので自身のスキルを高めましょう。
デビュー前にアシスタントとして経験を積むことを想定しているなら漫検(漫画能力検定)の漫画家アシスタント検定をめざすのもオススメです。
ベタやトーン、背景処理などアシスタントに必要な技術が身についているのかを客観的に判定してもらえます。